
こんにちは!
臨床検査技師のぴぃすけだよ。
一般的な健康診断ではあまりやらない採血の検査項目なんだけど、手術後やある病気を疑う時に重要視されるのが…
『dダイマー』
おそらく今この記事を読んでくれている人は「dダイマーの検査をした人」だと思うんだ。
その値がもしかして高かったのかもしれない。
そんな時に考えるべきは『深部静脈血栓症』というものになるんだ。
だから今日は、
・どうしてdダイマーの検査をするのか
・どういう理由があると高くなってしまうのか
・高い場合には疑われる深部静脈血栓症というのはどういう病気なのか
こういった内容で話していくね!
人間の機能の凝固と線溶
まずdダイマーの直接の話に入る前に1つ重要な人間の機能について覚えてもらいたいんだ。
それが
- 凝固
- 線溶
というものになるよ。
凝固はなんとなく固まるというのがわかるけど、線溶っていったいなにと思う人が多いよね。
実はdダイマーはこの線溶の方に関わってくるものだから、1つずつ詳しく話していくね。
最初に簡単に解説しちゃうと、、
- 凝固:血を固まらせる働きのこと
- 線溶:固まってしまった血液を溶かす働きのこと

どうしてせっかく固めるのに溶かしちゃうの?
こんな感じでお姉さんと同じように不思議に思った人もいると思うんだ。
出血時に起こる凝固と線溶
これはおそらくだけど、怪我をして出血してしまった時のことを想像したはずなんだ。
確かに怪我をしたときをイメージすると、出血を止めるためには血液を固めないといけないよね。
だからそれが溶けたらダメだと思うよね。
でもちょっとそこから考えていってほしんだけど、、
怪我をした場所は出血を止めるために血液が固まるよね。
ちなみにこの働きは凝固という働きだね。
でっ、そのあとってどうなっているかわかるかな?
例えば出血しているいうことは血管が傷ついて、その部分から出血しているってことだよね。
その出血を止めるために、凝固で血液を固めているわけだね。
でも怪我が治った部分を考えてみると、そこって血液の塊があるわけじゃないよね。
怪我をした部分は新しい細胞に置き換わって綺麗に傷を治しているよね。
そうしたら、さっきまで話をしていた出血を止めていた血液というのはどこにある?
考えてみると、どこにもないよね。
血液は固まって働きを終えたら今度は溶かされてなくす必要があるということだね。
この溶かす働きのことを線溶というわけなんだ。
だから怪我をして出血をした場合には、
- 出血を止める凝固
- その凝固したものを溶かす線溶
この2つが必要ということがわかるよね。
じゃあdダイマーはなんなのかというと、この線溶が起きた時に生み出されるものの1つになるんだよ。
dダイマーは血液の塊ができて、それが溶かされたら上昇するってことになるよね。
dダイマーを測定する理由は?
ここまでで『dダイマー』がどんな時にでてくるものなのかがわかったね。
次はなぜこの『dダイマー』を測定するのかを話していくね。
さっきも話したようにdダイマーというのは血液を溶かす時にでてくるものだったよね。
じゃあ怪我をして出血した場合にdダイマーを測定するのかというとそうではないんだ。
dダイマーを測定するのは最初でも話したけど術後なんかに多かったりするよ。

どうして術後に多いの?

血液の塊が出来やすい状態にあるからだね。
ちなみに血液の塊のことをここからは血栓と言っていくね。
血栓ができやすくなる理由
血栓が出来やすい状態ってどんな状態だと思う?
ちなみに飛行機も血栓が出来やすい状態ではあるかな。
血栓が出来やすい状態には3つあるんだ。
そのうち2つの項目が当てはまっていくと血栓が出来やすくなると言われているんだよ。
この3つの項目になるよ。
手術の場合は上のような状態そのものだから術後にはdダイマーを測定するということだね。
しっかり検査をすることで、血栓がないことを確認するというわけなんだ。
dダイマーを測定するということは、
体の中でもしかしたら血栓があるかもしれない
ということで検査をするというわけだね。
●飛行機ではなぜ血栓が出来やすい?
じゃあ飛行機の場合には、血栓が出来やすくなる原因のどれに当てはまるかというと、、
- 血液の成分がいつもと変わる
- 血流がうっ滞する
この2項目に当てはまることが多いよ。
飛行機ってあまりトイレに行きたくなくて、水を飲まない人が多いよね。
そうすると脱水によって血液の成分がいつもの状態と変わってしまうんだ。
あとはエコノミークラスなんかだと席が狭くて、足をあまり動かせないよね。
その結果として血液がうっ滞しやすい状況になっているんだ。
だから足に血栓が出来やすいというわけだね。
ちなみにこれをエコノミークラス症候群っていわれているものになるよ。
ただ後でも話すんだけど血栓が出来ることがエコノミークラス症候群じゃないから、それは注意してね。
dダイマーと血栓の関係
だけど1つ注意して欲しいことがあるんだ。
それがdダイマーが高いからといって、必ず血栓があるとは限らないということなんだ。

どうして?溶かす時にでてくるなら血栓があるんじゃないの?

うーん、ちょっと難しい部分なんだけどdダイマーは特異的な反応じゃないんだ。
『特異的ってどういうこと?』
これはその時だけ反応するかどうかってことになるよ。
例えばAっていうものがあったとするよ。
Aと反応するのがBだったら、それ以外には反応しないことを特異的な反応っていうんだ。
だけどAが他のCとかDとかにも反応をしてしまうことを非特異的な反応というわけ。
dダイマーは確かに血栓が出来て線溶が起こったときに出てくるもの。
だけどその他でも出てきてしまう。
非特異的な反応をしてしまうということだね。

じゃああまりdダイマーって検査しても意味ないの?
こう思ってしまう人も中にはいると思うんだ。
確かにこの話を聞くとそう思っちゃうよね。
でも検査をする必要はあるよ。
というのもdダイマーは特異性はそこまで大きくないけど感度はすごくいいんだ。
またわからない単語が出てきたね。
感度っていうのはAと本来反応して欲しいBとどれだけ反応するかということ。
だから今回のdダイマーで言えば、
高いから血栓があるということで検査をするわけじゃなくて、、
いつもと検査の値が変わらない、または低い
こういった時に血栓はおそらくないだろうということを確認するんだ。
あるのをしっかり見るんじゃなくて、ないことを確認する検査ということだね!
だからもしdダイマーの値が高いという場合にはエコーやCTといった他の検査を行うことで本当に血栓があるかどうかを確認するんだ。
深部静脈血栓症とはどんな病気?
ここまででdダイマーがどんなものかはわかったかな。
じゃあ最後にdダイマーで疑われる深部静脈血栓症というものについて話をしていくね。
深部静脈血栓症は名前の通り足の静脈の中の『深部静脈』という部分に『血栓』ができてしまうものだよ。
ちなみに
深部静脈血栓症=エコノミークラス症候群
と考えている人も多いんだけど全く同じものではないから注意してね。

えっ、違うの?

絶対に違うわけじゃないんだけど、どうして血栓があるとダメなんだと思う?

血液がそこで止まってしまうから?
実はそうじゃないんだ。
もちろん脳とか細い動脈を血栓で完全にふさいで血液がそこでしまうと問題なんだけど、、
深部静脈みたいに太い静脈では血栓で完全に血流がなくなるってことはあまりないんだ。
じゃあ深部静脈血栓症って何が問題になるかというと、、
その血栓が肺に行ってしまうことで、肺をつまらせてしまうことがあるんだ。
これが肺塞栓症というもので問題になるところなんだ。
基本的にエコノミークラス症候群っていうのは、この肺塞栓症というものまでなっている状態をいうよ。
こういう流れだね。
静脈に血栓ができたから悪いというわけじゃなくて、それが飛んでいって、詰まってしまうのが悪いということだね。
その場所にずっと留まっていても悪い影響はあるけど、飛んで行ってしまうと大きな影響が出てしまうことが多いね。
もし深部静脈血栓症やエコノミークラス症候群についてはもっと詳しくは別で話しているから、興味があればそっちで読んでみてね!
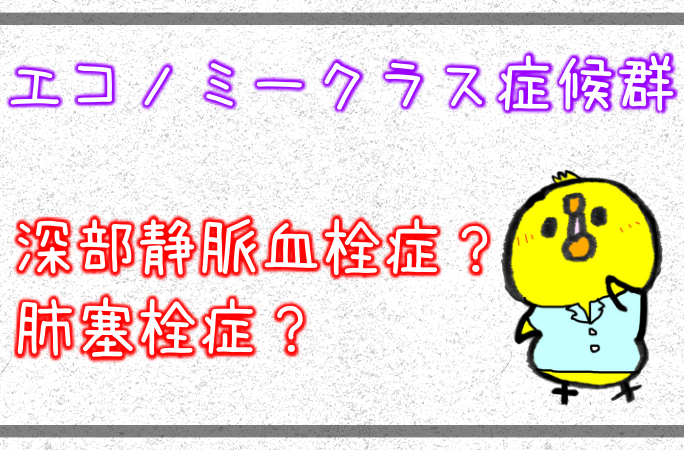
まとめ
今日はdダイマーについて話をしてきたよ。
・人間の体には凝固と線溶という働きがある
・dダイマーは線溶が起きると出てくる
・特異性は高くないが感度は高い
・感度が高いため値が高くなければ血栓はおそらくないと判断する
・疑うものとしては深部静脈血栓症というもの
・エコノミークラス症候群は肺塞栓症というものまで
こんな感じの話だったね。
なぜ検査するのかわからないと、もしちょっと値が高いとなった時に心配になるよね。
だけど今回のdダイマーのように少しでも気になるものがあれば高く数値が出て、その上で他の検査で確定させるというものもあるんだ。
こうやって検査は1つだけじゃなくて、いろいろな検査をすることでしっかり結果を出せるようになっているんだよ^^
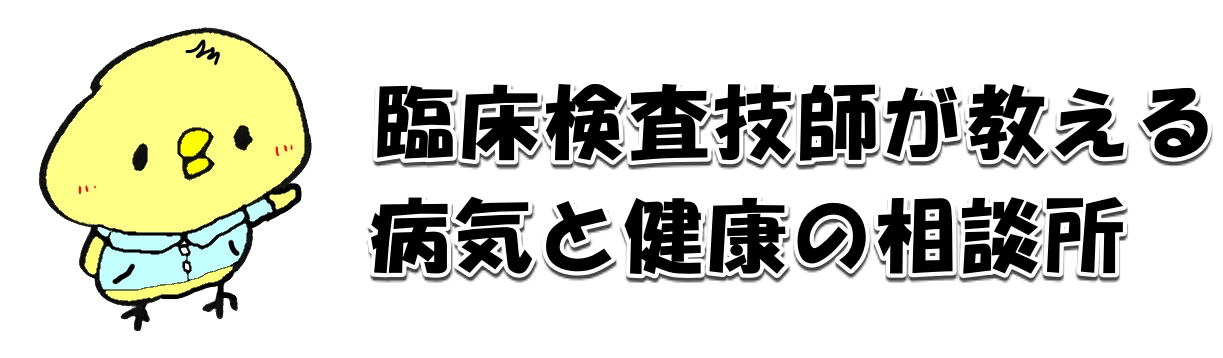
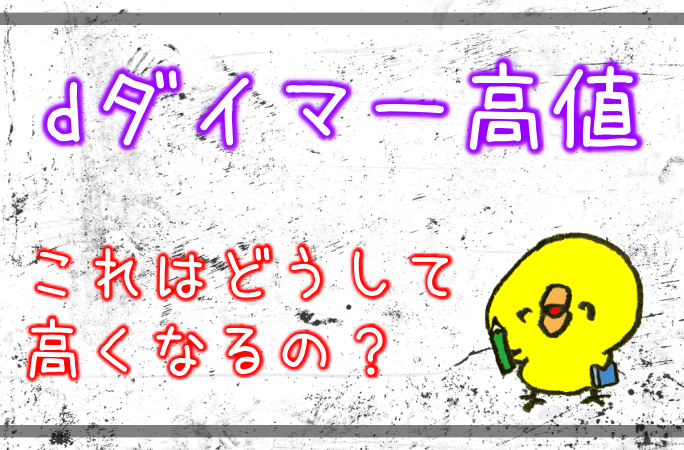
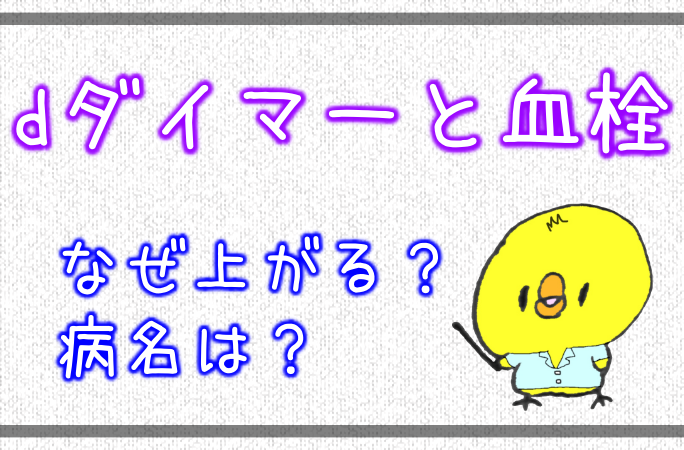
コメント