
こんにちは!
臨床検査技師のぴぃすけだよ。
今回は心電図の心房粗動について解説をしていくよ。
心房粗動はどういったイメージがあるかな?
おそらく『のこぎり』みたいな波形を想像したと思うんだ。
この心房粗動について
- そもそも心房粗動って何?
- のこぎり様の波形が出る理由
- 重要な伝導比
こういった内容で解説をしていくね。
心房粗動について
波形などを含めて、心房粗動について話をしていくよ。
ちなみに心房粗動は以前までは『AF』と表記されていたんだけど…
心房細動の『af』と区別がつきにくいから、今は『AFL』と書くことが多いんだ。
だからここからはAFLで書いていきますね。
AFLを略さないで言うと『atrial-flutter』となるから、これも覚えておいてね。
AFLの波形
AFLの波形から見ていくよ。
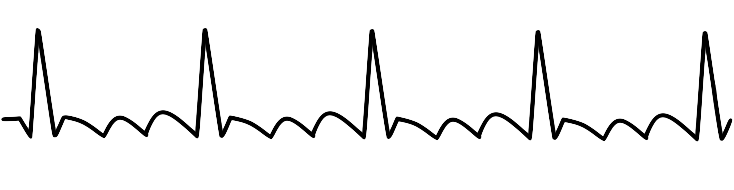
AFLはこんな感じの波形になるね。
QRS波とQRS波の間の部分がのこぎり様になっているのが特徴だね。
この波形『粗動波』をいうよ。

この波形の時に心臓はどんな動きをしているか分かる?
先に問題ない部分から考えると…
心電図を見てわかると思うけど、QRS波は通常と同じ形をしているよね。
だから心室の伝導に問題がないのがわかると思うんだ。
だから何か心房に問題がありそうだよね。
心房粗動っていうくらいだから当たり前だけどね。
具体的に心房でどんなことが起きているのかを図で表してみたよ。
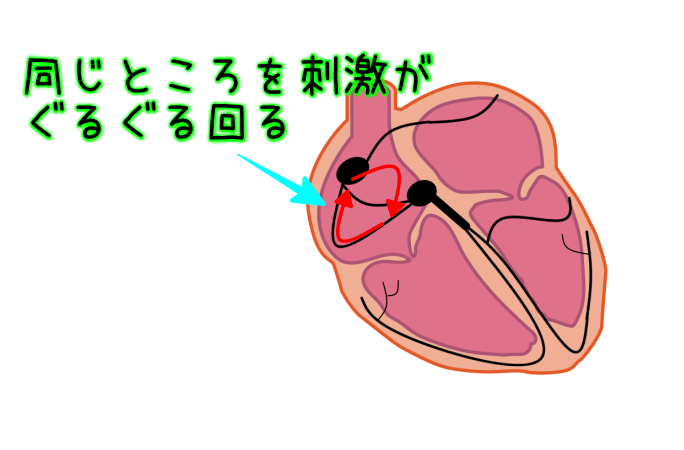
心臓の刺激というのは、洞結節から始まるよね。
AFLの場合はそうではなく心房のどこかから始まるんだ。
このどこかから始まった刺激が、心房内でぐるぐる伝わるので、粗動波というものがでるんだよ。
QRS波はというと…
そのぐるぐる回った何回かに1回が心室に伝わっていき、QRS波がでているということだね。
ちなみにこれは同じ頻度で、伝わっていくんだ。
毎回同じ場所をぐるぐる回って、一定の頻度で伝わっていく。
これがAFLというものになっているよ。

この同じ頻度で伝わるというのが伝導比に関わるよ
AFLの伝導比を考える
AFLでは、この伝導比がすごく重要になってくるんだ。
心房をぐるぐる回っていた刺激は、一定の回数で心室に伝わるって話したよね。
その何回で伝わるのかが、この伝導比というものになるんだ。
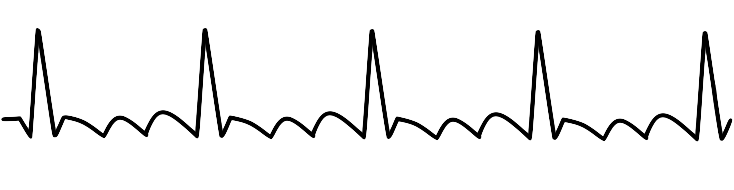

これはいくつ?
ちなみにこれは4:1のAFLとなるよ。
AFLの中で多いのが2:1や4:1になるんだ。
次はなぜ伝導比を見ていく必要があるかってことだね。
伝導比で分かること
これは『心拍数』に関わってくるんだ。
RR間隔をしっかりみれば、心拍数は自然とわかる。
でも実は何対何かでもだいたいわかるんだよ。
というのもこのAFLって
1分間に約300回の粗動波
が出ていると言われているんだ。

もし4:1なら心拍数はいくつくらいになりそう?
仮に4:1のAFLなら、この300の1/4がおよその心拍数になるんだ。
だから75回/分という感じだね。
心拍数が適切なら、心臓から血流を送ることが出来る。
だけど早すぎたり遅すぎたりすると危険だよね。
だからこういった部分から、心拍数を読み取ることも重要だよ。
まとめ
今回はAFLについて解説をしてきたよ。
最後にまとめておくね。
・ぐるぐる刺激が回り粗動波が認められる
・心室に一定間隔で伝わるためRR間隔は等しい
・粗動波は1分間に約300回
・伝導比は2:1や4:1が多い
こんな感じだったね。
心房細動と粗動が意外と迷ってしまう人が多いから、1つ1つしっかり確認して覚えていってね。
●関連記事
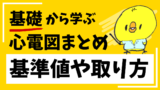
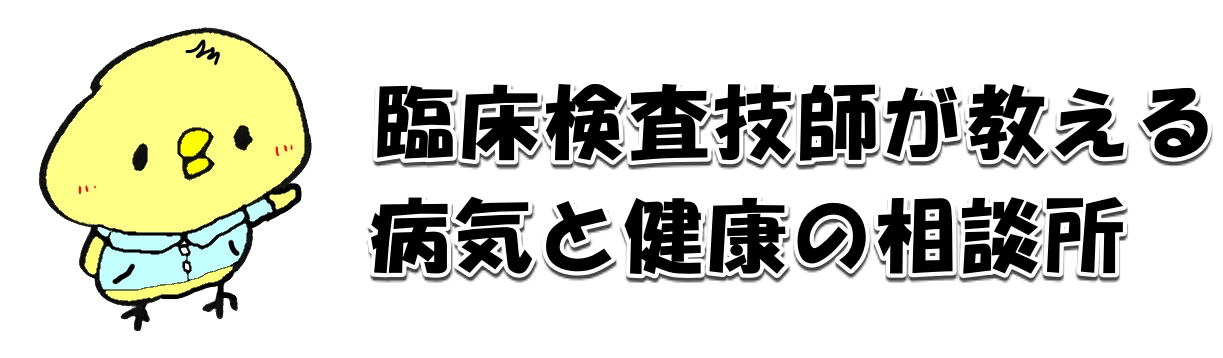
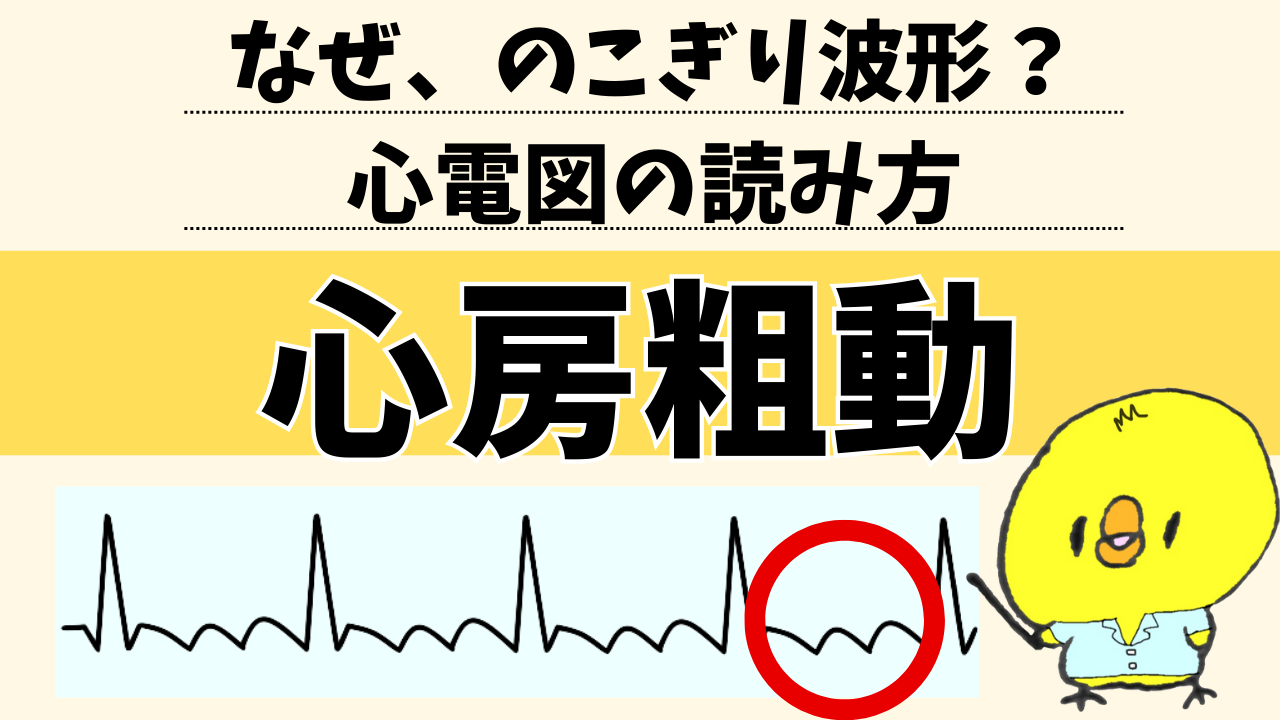


コメント