
こんにちは!
臨床検査技師のぴぃすけだよ。
僕が臨床検査技師になるまで、この項目って知らなかったんだけど、意外とみんな気になっている項目。
『dダイマー』
この言葉を知っている人は、dダイマーがなんとなく血栓と関係があるということは知っている人が多いよね。
でも実際にどうして血栓ができると高くなってしまうのかということは知ってる?
今日はそんなdダイマーについてdダイマーがどんなもので、なぜ高くなるのかを話していくよ。
dダイマーを知るために!
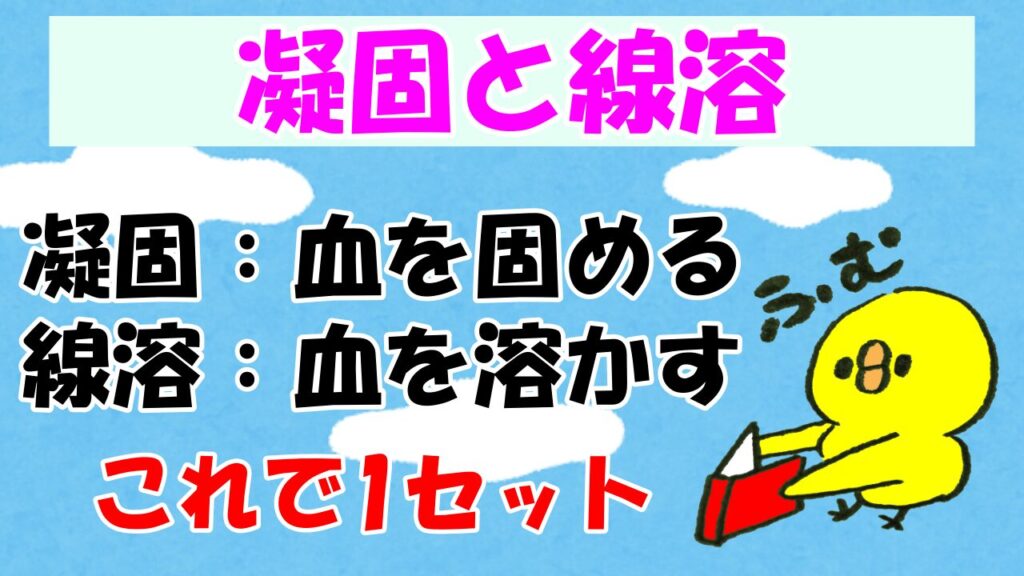
じゃあdダイマーについて話をしていくよ!
となりたいんだけど、実はdダイマーを知るためには、人間の体のある機能を知らないといけないんだ。
そのある機能というのは、血液の凝固と線溶という話になるんだ。
凝固はなんとなくわかるけど、線溶って何って人も多いよね。
なぜか医療用語ってこうやって難しい言葉が多いんだよね。
簡単に言ってしまうと、『固まる』ことと『溶かす』ことっていう意味になるんだ。

固まるはわかるけど、なんで溶かすの?
というか溶けるって何が?

ちょっとパニックになっているね。
じゃあどうして人間の体では血液が固まったり溶かしたりという機能があるのかを順を追って話していくね。
凝固と線溶
まず前提としてこれはしっかり覚えてね!
まずここまでは大丈夫だよね。
固まるっていうのはなんとなく理解できると思うんだ。
怪我とかした時に血が固まって出血が止まるよね。
あれを想像してもらえれば大丈夫だよ。
実はあの時には凝固系っていって、すごくたくさんの因子(成分のようなもの)が働いているんだよ。
出血を止めるために血小板が固めるっとか聞くと思うんだ。
確かに血小板も固めることに使われているけど、それ以外にもたくさんあるってことだね。
こうやって考えると人間の体ってすごいよね。
固まるということはわかってもらえたと思うんだけど、なぜ溶かすかということだよね。
「せっかく固めたのに溶かしたら意味ないんじゃないの?」
こう思う人も多いと思うんだ。
だけど実はこれって逆なんだ。
ちゃんと理解すると溶かさないとまずいというのがわかると思うよ。

もし怪我をして、その部分に血液が固まったままいたらどうなると思う?

血が止まる!

えっと、じゃあ怪我した部分が新しい細胞で治ったら、その固まった血液はどうなっちゃう。

あっ…。
お姉さんは気づいてくれたね。
みんなも大丈夫だよね。
怪我したら新しい細胞でその部分って綺麗に治るよね。
だから一時的に止めていた血液の塊はいらなくなってしまうわけだね。
だから固めた血液を溶かさないと、ちょっとまずいことになっちゃう。
もしかしたらその塊が血管内を飛んで行ってしまったら血栓になっちゃうかもしれないし。
だからそうならないように、人間の体の機能には
- 血を止める:凝固
- それを溶かす:線溶
ってものがあるということなんだ。
dダイマーとは?
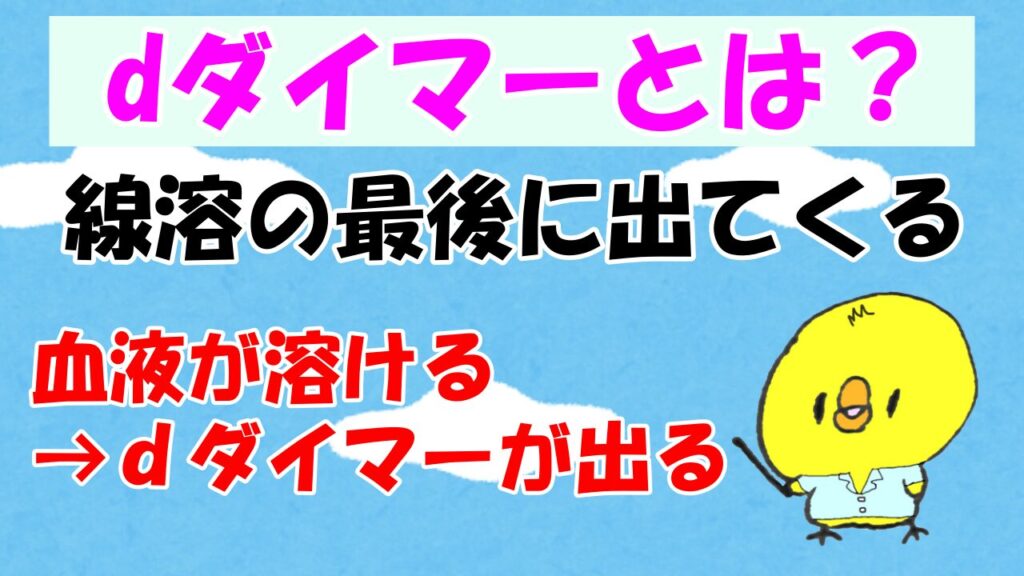
そこまでわかったところで、このdダイマーというものが何かを話していくよ。
dダイマーは簡単言ってしまうと、線溶の最後に出てくる物質と覚えてくれれば大丈夫だよ。
血液が溶けたら出てくるってこと。
例えば体の中で血栓ができたりする病気があるよね。
そういう時には血が固まるだけじゃなくて、同時に溶かすこともしているんだ。
だから血栓ができているかどうかの確認としてdダイマーを確認するというわけだね。
ただ血栓だけじゃなくて、手術をした後なんかは上がってしまったりするんだ。

手術後って基本的に血栓ができやすい状況になっているから、ちょっときつめのストッキングをはいたりするのは知ってる?

知らなかった。
血栓ができやすい条件っていうのがあって、手術後はその状況になっていることが多いんだ。
だから血栓ができないように血液がしっかり流れるようにきつめのストッキングを履くようにしているわけだね。
それでもdダイマーが上がってしまっている時がある。

それってそれくらいやっていても血栓ができているってこと?
気になるのはそこだよね。
dダイマーが高いと必ず血栓があるの?
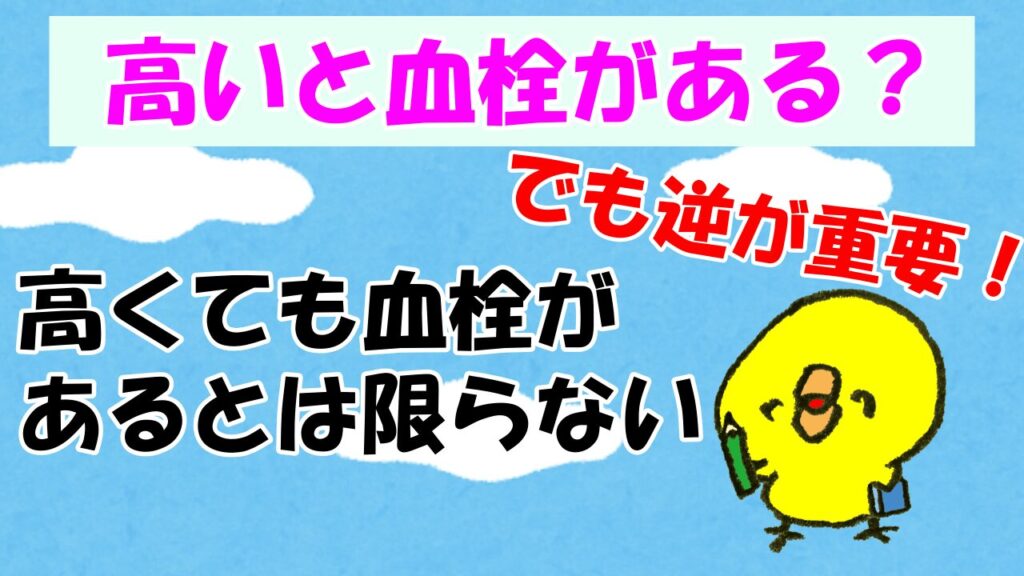
なんとなくdダイマーについてわかったと思うから、最後に血栓との関係について少し話していくよ。
結論から言っちゃうと、
dダイマーが少し上がったからと言って血栓があるとは限らないんだ。
確かにdダイマーは線溶の最後に出てくるもの。
なんだけど、炎症が起きたりとか体に何か異常があると上昇してしまうことがあるんだ。
よくこういうのを僕たちは非特異的反応とか言っているよ。
すごく上昇している時は血栓がある確率が高かったりするけど、少しの上昇だと血栓がないことの方が多いかな。
dダイマーの考え方
どのくらいまで上がると血栓があるかという基準だけど…。
この基準値なんだけど病院によって違うんだよね。
だからこれとは言えないけど10とか20μg/mlだと血栓がないことが多くて、数百とかあると血栓があることが多いかな。
このdダイマーで判断するというよりも、、
血栓があるかどうかの確認については、例えばCTの検査だったり多いのはエコーの検査かな。
直接血管を見て、血栓がないかを確認するんだ。
意味合い的にはdダイマーは値が高いから血栓があるというわけじゃなくて、逆の意味で測ることが多いんだ。
線溶が起きればdダイマーは上昇するよね。
血栓ができてれば基本的に線溶は起きるよね。
だから逆に考えて
- 再検査ではdダイマーが以前の結果と変わらない
- 初めてならかなり低い値
これなら血栓はないだろうと判断するんだ。
何かあるかどうかを検査するわけじゃなくて、ないことを確認するための検査ということなんだ。
だから術後なんかは、よくdダイマーを測定しているのはそういう理由があるからだね。
ただ難しい部分として必ずこうなるとは言い切れないから、しっかりお医者さんの話を聞いてね!
まとめ
今日はdダイマーというものについて話をしてきたよ!
・人間の体には血を固める作用と溶かす作用がある
凝固:血を固める作用
線溶:血を溶かす作用
・線溶の最後にdダイマーが出る
・dダイマーが少し高いからと言って血栓があるとは限らない
・dダイマーが低い場合は血栓がないことになる
こんな感じだったね。
凝固とか線溶とかちょっと難しい話もでてきたけど、なんとなくdダイマーがどんなものか理解してくれたかな。
僕たちが検査する時にも、こういう値はちゃんと見て検査しているんだ。
1つの検査だけではわからないことも、こうやっていろいろな検査をすることで判断をすることができる。
医療ってそういうものなんだよね。
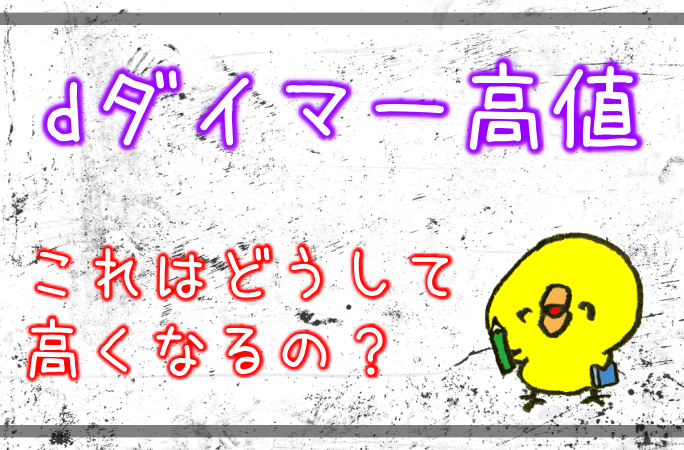
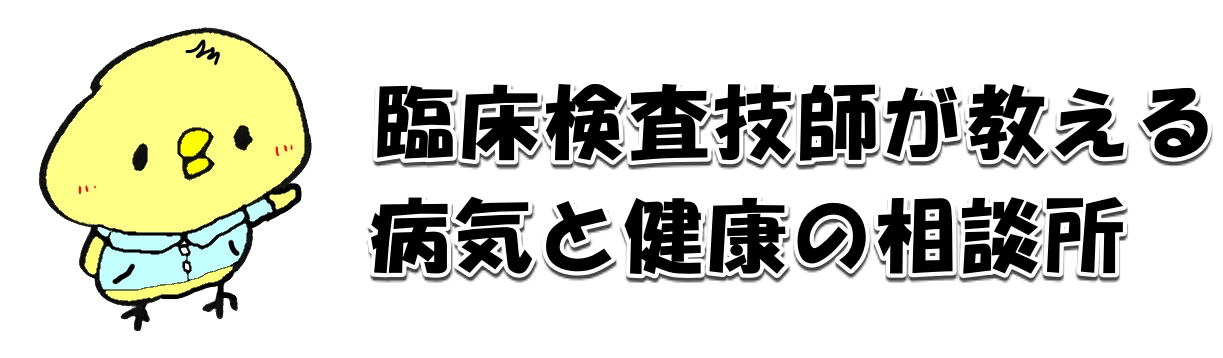
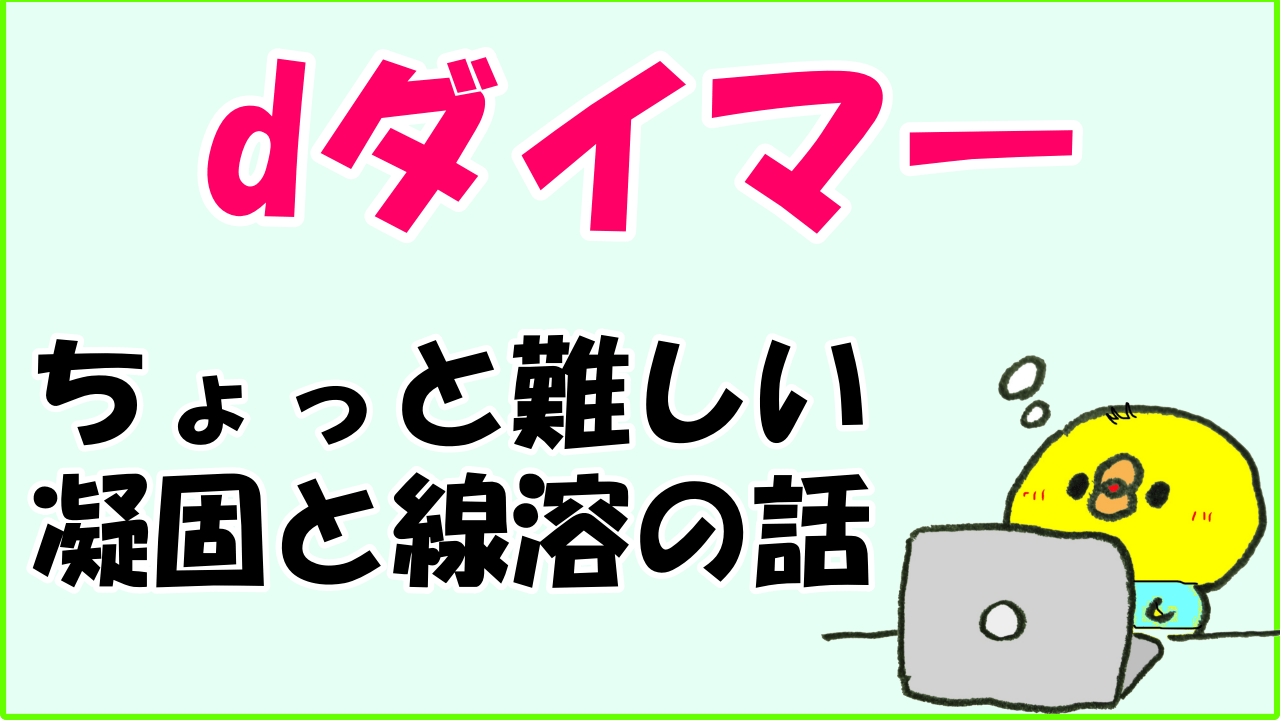
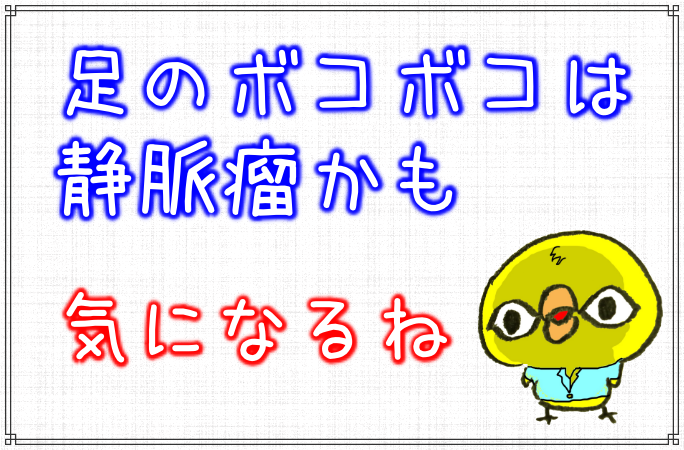
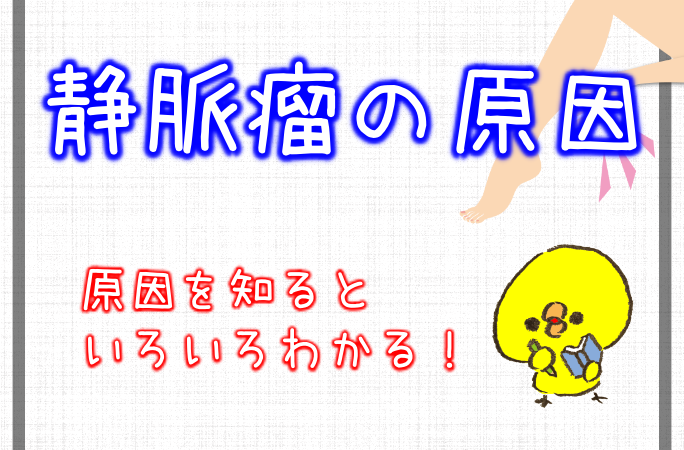
コメント
とてもわかりやすい解説をありがとうございます。私はdダイマーの値が高くて、今回移植ができませんでした。お水をあまり飲まないタチなのと、前日岩盤浴1時間、お風呂、蒸し風呂サウナに入りました。また、何度か血液検査をしております。その場合、dダイマーの値があがってしまうのでしょうか?尚、今現在バイアスピリンを投薬しております。dダイマーを下げる方法でできることはあるのでしょうか?なにかよい方法があればご教授いただきたく思います。よろしくお願い致します。
dダイマーについては少し難しい部分があるんだよね。
というのもdダイマーというのは、これが高いからと言って血栓があるというものではなくて、値が以前と変わらないから血栓ができてないだろうという意味があって検査する項目になるんだ。
今回の場合だとバイアスピリンを使っているということだから、何か病気などがあって投薬しているということだよね。
だからもし下げるにはdダイマーをどうにかするというよりも、その原因となる何かを治療することが重要かなと思うよ。
僕が言えるのは個人の一意見だから、しっかりお医者さんに相談してみてね^^